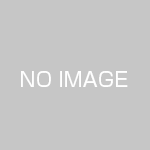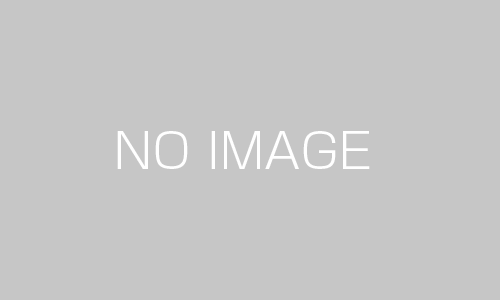高圧キャビネットは高圧電力を利用する施設などで設置されます。
高圧キャビネットとはなんなのかや、設置のための基準があるのかなどを見ていきましょう。
高圧電力を利用する場合は、高圧キャビネットが必要になるケースも多く、正しい知識が求められます。
いざ高圧キャビネットが必要になった時、スムーズに導入するためにも仕組みや基準について知っておきましょう。
高圧キャビネットとは?
高圧キャビネットはキャビネットやピラボックスとも呼ばれています。
呼び方が違っても同じものを指しています。
6,600ボルトの高圧電力を利用する場合、電力は電柱に繋がれている電線から供給される場合と、地中の電線から供給される場合の2パターンがあります。
高圧キャビネットは地中から供給される場合に使うことになる設備です。
見た目は大きな箱のような形状で、この箱の中で電力会社の配線と、各施設の配線をつないでくれます。
配線をつなぐことで電力を使えるようにしているわけです。
高圧キャビネットの中にはいくつかのスイッチが取り付けられていて、このスイッチをオン・オフすることで動きます。
箱の左側部分には電力会社の配線が、右側部分には各施設の配線があり、高圧キャビネットの中でそれぞれをつなぐ仕組みです。
地中から電力の供給を受ける場合は高圧キャビネットが必須となります。
供給の状態によっては高圧キャビネットを導入する必要がありますので注意しましょう。
高圧電力を利用する場合に必要な設備ですので、高圧電力を利用しない一般家庭などでは活躍の機械もありません。
ただし、一般家庭であってもなんらかの理由で高圧電力を利用し、さらに地中から電力の供給を受けるなら高圧キャビネットを新たに設置する必要が出てきます。
高圧キャビネットの設置基準について
では高圧キャビネットの設置基準について考えてみます。
高圧電力を使う場合、電柱から供給を受けるだけではなく、地中からも供給してもらえるわけですが、高圧キャビネットは地中から供給を受ける時に使います。
そのため設置基準の1つとして、高圧電力を地中から供給してもらう場合が挙げられます。
もし高圧電力が必要で、さらに地中から供給を受けるなら高圧キャビネットを設置しなければなりません。
高圧キャビネットの中には電力会社側の設備と、私達利用者の設備が左右に設置されていて、これも設置基準に関わっています。
その時に重要な言葉となるのが責任分界点です。
責任を分界する点、つまり電力会社と私達で責任を分けるポイントのことです。
高圧キャビネットの左側の設備が電力会社のもので、右側の設備が私達のものとなりますが、その間に責任分界点が設けられ、保安上の責任を区別するために必要となります。
何かあった場合、電力会社と私達側でどちらに責任があるのか、責任分界点があれば明確になるのです。
そのため責任分界点は高圧キャビネットの中に設置されます。
電気設備の維持や管理については、電力会社と電気の利用者側それぞれに責任が生じます。
どちらに責任があるのかわからない状態だと、トラブルにもなってしまいますので、トラブル予防のためにも設置されていると考えれば良いでしょう。
高圧キャビネットを設置するなら責任分界点も設けておく必要があり、設置基準の1つと言えます。
高圧キャビネットの寸法はどのくらい?
高圧キャビネットは各メーカーごとにさまざまなタイプが用意されています。
寸法もタイプによって違いますので、明確に寸法が決められているわけではありません。
大きさが商品ごとに違うことになりますので、高圧キャビネットを導入する場合は寸法もしっかりチェックしておく必要があります。
施設内に設置することになりますので、適切な寸法のものを選ばないと、スペースを余分に取ってしまったりします。
小さい分にはそれほど問題もありませんが、大きすぎると設置スペースが不足するケースも考えられます。
カタログを見るなどして、あらかじめ寸法をチェックしておきましょう。
また、同時に高圧キャビネットを設置するスペースがどのくらい確保できるのかも調べておきましょう。
設置スペースに合わせて最適な寸法のものを選ぶのが基本です。
いずれにしても高圧キャビネットは比較的大きな設備ですので、小型のものでもそれなりの寸法になります。
充分なスペースがないと設置できない可能性もあるので、その点には充分注意しておきましょう。
高圧キャビネットは高圧電力を地中から供給してもらう場合に必要になります。
変圧を行うなどではなく、電力会社が供給する高圧電力を受け取るという役割を果たしています。
そのためキャビネット内には、電力会社が責任を負う部分と、利用者側が責任を負う部分があり、その間に責任分界点が存在します。
責任分界点によって責任が区別されている点も覚えておきましょう。
これによって電気の管理責任がどちらにあるのかはっきりします。