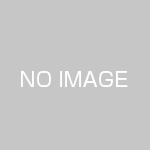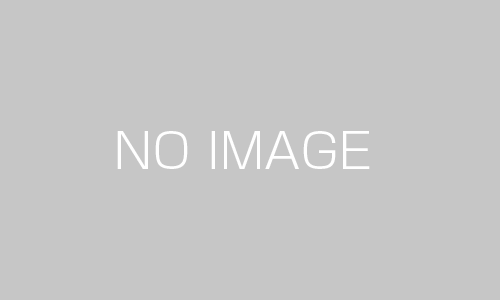軽油はディーゼル車の燃料です。
ディーゼルエンジンは圧縮した空気に軽油を噴いて自己着火させます。
軽油は噴射したときにすぐに着火する必要があります。
その着火のしやすさを表す指標がセタン価です。
このセタン価は0から100の値をとり、この数値が高いほど自己着火しやす
いです。ディーゼルエンジンにとってセタン価は50以上が望ましいです。
なお冬に軽油は凍結することがあります。
「東京で軽油を入れて長野へ泊まりがけでスキーに行き、翌日の朝にエンジン
がかからない」なんてこともあるかもしれません。
これは、軽油は気温が低いと軽油中のパラフィンという成分が結晶化してシャ
ーベット状になり、それが原因で燃料フィルターが詰まってしまうためです。
そのため軽油は規格で使用気温範囲が決まっています。
JIS2号軽油:−5℃から40℃
JIS3号軽油:−15℃から20℃
JIS特3号軽油:−30℃から20℃
季節や地域によって使用する軽油が違っているため、ディーゼル車で寒冷地へ
行くときは現地へ着くまでに燃料が半分以下になるようにして、現地の寒冷地
仕様の軽油を入れる必要があります。
ガソリン車に乗っている方がほとんどなので、普通の人は知らないですよね。
私も知りませんでした。
またサルファーフリーという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
このサルファーフリーのサルファーとは硫黄の英訳(sulphur)です。
硫黄成分が10ppm以下の軽油をサルファフリーと呼びます。
ppmとは濃度を表す単位で1ppmは0.0001%のことです。
軽油中に含まれる硫黄成分を減らすことが最近のトレンドになっています。
1990年代初めのころは、軽油中の硫黄成分が2000ppmでした。
なぜ、軽油中の硫黄成分を減らすのか。
その理由は、年々厳しくなるディーゼル車の排気ガス規制と関係があります。
排気ガスをきれにしようとすると、どうしてもこの硫黄が邪魔をします。
どんな邪魔をするのかというと、
・硫黄成分が硫黄酸化物としてエンジンから排出され排気ガスが汚くなる
・硫黄成分がエンジンの排気ガスの浄化装置の機能を低下させる
などが挙げられます。
これらを防ぐために軽油中の硫黄成分を減らしているわけです。軽油は排気
ガス規制の流れに乗って今変わりつつあるところです